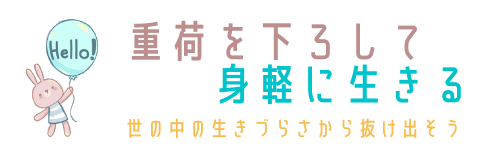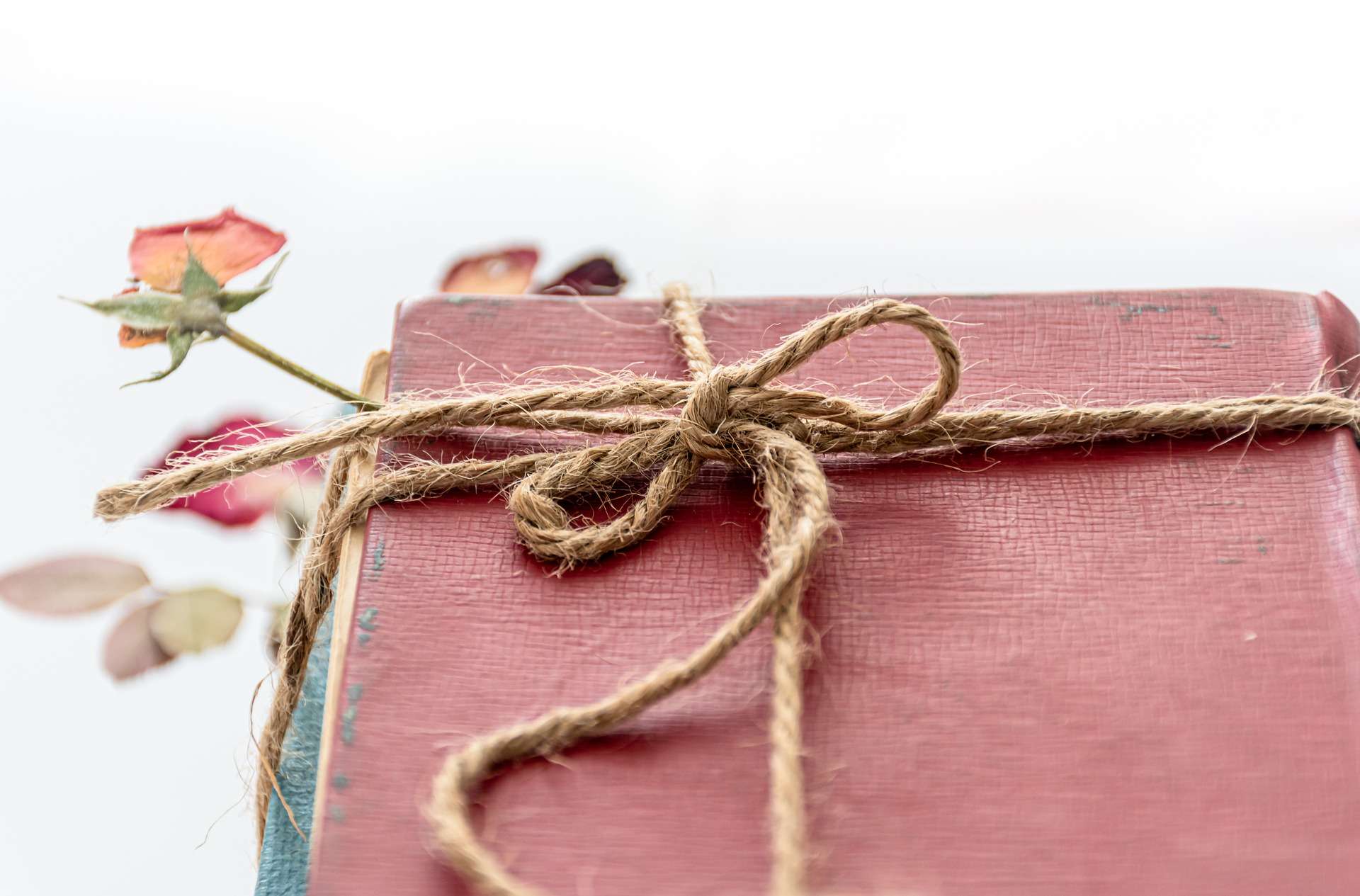難関資格は挑み始めると、後に引けなくなりますよね。
弁理士もそのひとつで、私は4年も費やした末に、挫折しました(^^;)
司法試験並みの難関資格「弁理士」
この記事をご覧になっている方は、弁理士という資格はご存知でしょうが、世間的には馴染みがありませんよね。
私も、弁理士試験を受験すると周りに伝えた時には、「便利屋を目指すって、突然どうしたの?」と真顔で言われたものです(笑)。
ちなみに弁理士とは、知的財産権を扱うスペシャリストでして、難易度は司法試験並みと言われます。
ちなみに、試験形式も司法試験と似ていて…
- 短答試験(1次,マークシート方式)
- 論文試験(2次,記述方式)
- 口述試験(3次,面接方式)
と3段階に分かれています。
これを、1年をかけて順に通過していき、晴れて最終合格という難関資格です。
ただ、独自の試験免除制度が設けられている点で、司法試験よりは精神的に楽かな…、と個人的に思います。
例えば、短答試験を通過し論文試験で失敗した場合、翌年は短答試験が免除され、論文試験から受けられるのです。(10年以上前の話ですが、現在もそうなのかな?)
弁理士の資格は自分の将来に必要?
ところが、2次の論文試験が最大の壁でして、大概の人はココで2年分の免除を使い果たし、挫折してしまうと思われます。
免除を使い果たした絶望感は、とても耐え難いものでして、一から受け直す気力は残っていないのです。
私がまさに、それを経験して挫折した一人です(汗)。
気力を搾り出して受け直す人は、それはそれで素晴らしい志だと思います。
少なくとも私には、その能力がありませんでしたから…。
ただ、その前に一度立ち止まって、考え直してみることをお勧めします。
- さらに数年の努力で実る見込みはあるか?
- 独立開業し成功させるビジョンはあるか?
- そもそも弁理士の資格は本当に必要か?
実は弁理士の資格が不要な人
まず、独立開業が譲れない目標にあるなら、受かるまで頑張るしかないでしょう。(資格がないと実現できませんから。)
ここで、考え直してみた方が良いのは、企業などの組織に属していて、知的財産権に携わっている人 (もしくは、将来その方向性にある人)です。
例えば、会社内の職務として特許出願をする場合、必ずしも弁理士の資格は必要ありません。
簡潔に言えば、弁理士の資格が必要なのは、第三者の特許出願を代理する場合だからです。
つまり、この先も企業に属する人生設計で、第三者の出願代理などを行わないなら、弁理士の資格を取得する必要はないのです。
これが仮に、宅建士くらいの難易度ならば、受かるまで挑み続けるのもアリでしょうが、弁理士は膨大な時間と労力を削がれます。
人生は有限であり、若さは二度と取り戻せない…
意地だけで受験し続けているなら、考え直した方が良いと思うのです。
企業に属するなら知的財産技能士がお勧め
とは言え、何年も弁理士試験に挑んだ人なら、そのまま身を引くのは悔しいのも、痛いほど分かります。
少なくとも、投資した努力を形に残したいと思うのが、正直なところだとお察しします。
そこで、弁理士試験を挫折した私が取得したのは、 知的財産管理技能士(知財士) という資格です。
この資格は、「知的財産管理技能検定」という名称でしたが、「技能士」と格上げ?されたのです。
もちろん、弁理士のような専権業務(資格がないとできない業務)は無いですが、ここ数年でかなり知名度が上がっている資格です。
第三者の代理業務を考えていないなら、検討する価値が十分にあると思います。
同資格の概要としては、3級から1級に分かれており、3級から順に受ける必要があります。
試験問題の内容は、弁理士の試験と比べて、かなり実務に近いと感じました。
ちなみに、2級の難易度は、弁理士の短答試験を通過した人なら、追加の勉強をせず余裕で合格できる程度です。
1級については、実務経験が受験資格に課せられているので、私は受験できませんでした。
つまり、企業で知的財産権に携わっている人ならば、とてもコストパフォーマンスの高い資格だと思うのです。
第三者の代理業務をする予定がないならば、弁理士試験に多大な労力をかけるより、知財士を確実に取得して他の事に時間を使う方が、人生にとって有益ではないでしょうか?
独立開業しないなら知的財産技能士で十分
弁理士という資格は、コストパフォーマンスが悪いと言われることがあります。
私が、弁理士試験の予備校に通っていた時の講師も、同じようなことを言っていました。
労力とお金を投資した割には、合格した後も大して給料が上がらなかったとか、活かせる仕事に就けないことが多いそうです。
ですから、本当に弁理士を目指したいのであれば、相当なビジョンや覚悟が必要と言えそうです。
一方、具体的なビジョンが無いのであれば、知財士に目標を切り替えた方が賢明でしょう。
今回は、弁理士の短答試験を通過した人向けに、色々と経験談を書いてみました。
ただ、これから弁理士を目指そうと考えている人も、漠然とした動機なら再検討をお勧めします。
繰り返しになりますが、独立開業しないのなら知財士で十分、ひとつの判断基準ですね。
とは言え、短答試験の経験もない状態では、知財士の2級は難しいと思われます。
独学で挑むのが不安でしたら、通信教材を利用することをお勧めします。
一度きりの人生、難関資格に挑む前には、慎重に考えましょう!
もちろん独学も可能です♪
弁理士試験の受験経験や、知財について一通りの知識がある人なら、独学でも十分に合格を狙えます。
私の場合は、この本だけで事足りました☟