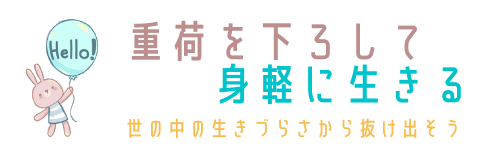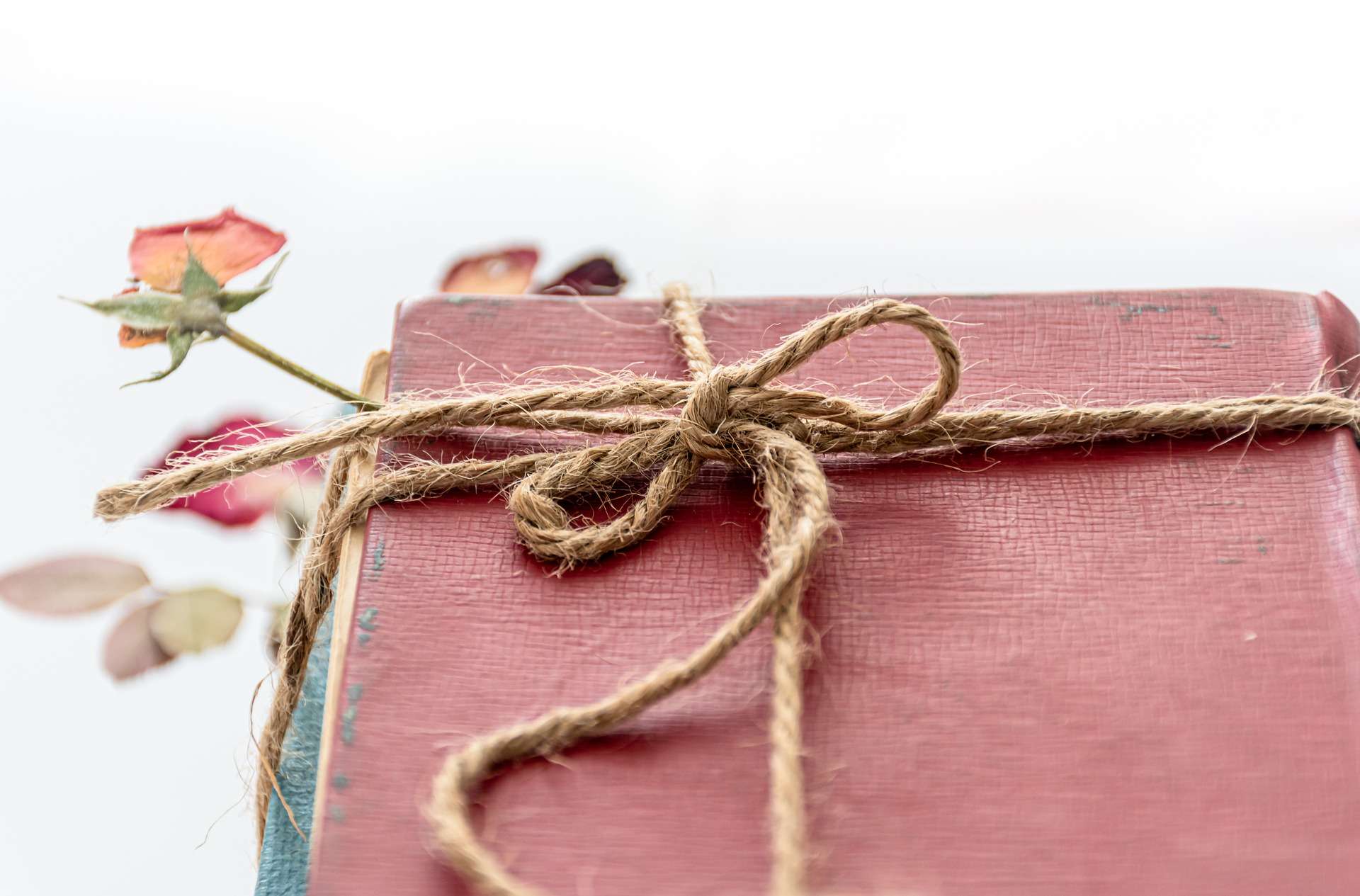資格試験の直前期に大事なのは、当日のコンディションをいかに合わせるか?、コレに尽きます。
スポーツでよく言われる「心技体」は、資格の勉強にも当てはまるんですよね。
読書の秋は資格試験シーズン
秋といえば、読書・食欲・スポーツが挙げられますが、資格の秋と言ってもいいほど、資格試験が多いシーズンです。
私も、今までに数々の資格試験を受けてきましたが、10月頃が一番多かったように思います。
ちなみに、私が受験した資格とその結果は、以下の通りです。
- 弁理士試験(一次試験は合格♪,二次試験で挫折…)
- 知的財産管理技能士(3,2級ともに一発合格!)
- 個人情報保護士(一発合格!)
- 宅地建物取引士(二度目で合格♪)
- 日商簿記検定(3,2級ともに一発合格!!)
なお、TOEICも受験経験がありますが、試験対策法がかなり独特ですから、ここでは挙げませんでした。
資格試験で大事なことは「段取り」
資格試験の方式として定番なのは、やはりマークシート方式でしょう。
司法試験をはじめ一部の難関資格では、論文や口頭弁論の方式もありますが、それでも一次試験にはマークシート方式が採られています。
ゆえに、マークシート方式に慣れておくことは、効率的に合格へ近づくために必要な作業といえます。
本記事では、一部の特殊な試験方式については他サイトさんにお譲りし、マークシート方式に絞って私の経験談を書いていこうと思います。
まず、資格試験で必要な段取りとは、どういったものでしょうか。
私の経験上ですが、直前1ヶ月の状況と試験当日の過ごし方が、試験の出来ばえに大きく影響します。
そこで今回は、難関資格である弁理士試験で培った経験を基に、その後の資格試験で必ず行っていることを書き出してみました。
これから試験本番を控えている方に、少しでもヒントになれば幸いです。
試験直前期のブレない「やるべきこと」
これから挙げていくことは、試験のコツとしてよく書かれていると思います。
それだけに、マークシート方式の試験に限らず通ずることなので、改めてまとめました。
苦手項目を集約した1冊を読み込む
まず、あとはコレに集中すれば万全!というものを、直前1ヶ月前までに完成させる必要があります。
1冊のテキストに書き込んでいくとか、別にノートを作って書き出すとか、方法は色々あると思います。
難関資格になると、1冊にまとめるのは難しいかもしれませんが、情報を集約(一元化)させることが大事なのです。
そして、直前1ヶ月は新たな書籍には一切手を拡げない、ということです。
焦る気持ちは分かりますが、こんな直前になって手を拡げても身に付かないどころか、不安材料が増えて精神衛生上よくないのです。
試験当日の時間配分で模試を受ける
例えば1~2週前の日曜日に、試験当日と同じスケジュールで、模試を受けることをお勧めします。
予備校の模試に参加する必要はなく、書店で購入したもので構いません。
ここで、資格試験の日時についてですが、日曜日の昼から開始されるパターンが多いです。
この微妙な時間帯が曲者でして、昼食をとるタイミングが難しいんですよ。
そこで、模試を受ける1日は、試験当日と同じ段取りで過ごすのが、一番の精神安定剤になります。
試験会場や周辺環境の下見をする
これについては、会場が遠方でない限り、一度はやっておくべきでしょう。
道に迷わないためというよりは、周辺で時間をつぶせる喫茶店や、飲み物などを買うコンビニを把握しておくためです。
その程度なら、グーグルマップで事足りるかもしれませんが、事前に足を運んでおく安心感には代えられません。
しかも当日は、周辺の店が受験者でごった返す恐れがあるので、そのイメージトレーニングもできます。
なお、予め必要だと分かっている飲み物などは、前日までに買い揃えておく方が安心です。
試験当日のブレない「過ごし方」
いよいよ、試験当日の朝になりました!
ここでは、着席時間が12:30,試験開始が13:00という、よくあるパターンに仮定して書いてみますね。
まず朝食をきちんと食べる
朝食はあまり食べないという人も、頑張ってしっかりと食べておくことが大事です。
なぜなら、先ほども書きましたが、昼食のタイミングが難しく十分に食べられないからです。(詳しくは後ほど…。)
食べるものについては、私は特に気にしていませんが、ジャンクフードは避けましょう(笑)。
早めに会場周辺へ向かう
会場周辺に、待機できる喫茶店などを把握しているなら、着席時間の2時間ほど前には到着しましょう。
そうすれば、会場までの移動時間を差し引いても、喫茶店で1時間ほどリラックスできます。
直前1ヶ月に活用した1冊を、最終チェックするのもいいですね♪
会場に到着して昼食をとる
目安としては、着席時間の30分前には到着しておくのが、一番安心かつ効率的です。
いったん自分の座席を確認したら、会場内の休憩スペースなどで簡単な昼食をとりましょう。
私の場合は、ブラックコーヒー,アーモンドチョコレート,バナナの3つが定番です♪
下手に炭水化物をガッツリ食べると、試験中に眠くなってしまいますから…。
スポーツと同じく資格試験も「心技体」が大事
ここまで来たら、あとは試験本番に専念するのみ!、ですね。
実は、試験本番中の段取りもあるのですが、本記事のテーマから脱線してしまうため、別の記事にまとめました☟
ともかく、以上の段取りを踏むか否かで、試験中の安定感が全然違ってきます。
一見、勉強とは関係ないことも含まれますが、精神面や体調面に関することで、決して侮れません。
言ってみれば、心技体をバランスよく整える、ということです。
「心技体」とは、スポーツの分野でよく言われることですが、資格試験についても大事なことです。
心(精神状態)・技(習熟度)・体(健康状態)は互いに繋がっていて、どれかひとつが不足していても、最高のパフォーマンスは出せません。
今回の記事では、「心」に重点を置いた内容で書いたつもりです。
「技」については各資格でノウハウがあるでしょうし、「体」については人それぞれの対処法があると思います。
これら3つをバランスよく整えて、合格という目標を達成しましょう(^^)/